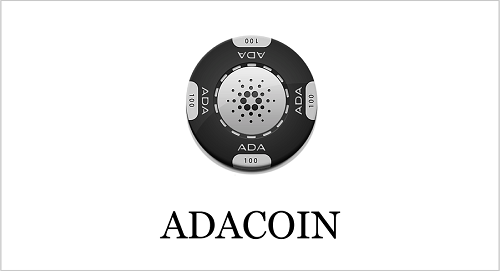モバイルアプリや、コンピュータの画面から離れたくない人のためのデスクトップ版で簡単にウォレットにアクセスできるなど、これまで以上に取引が簡単でアクセスしやすくなる機能を備えています。 Binanceで取引する3つの理由 Binanceは、近年人気を博している暗号化取引所です。暗号通貨を取引するための使いやすいプラットフォームで、他では見られない証拠金の貸し出しサービスも提供しています次の3つの理由を見れば、この人気の暗号通貨市場を検討する価値があることが納得できるでしょう。1) 証拠金貸付 – 自分の好きなコインを使ってお金を借りることができるので、価値が安定していたり、(ビットコインのように)ボラティリティーが高いコインであれば、必要なときに融資を受けるのに問題はありません。 2) 低い取引手数料 メリット1 取扱通貨が豊富 Binanceの最も優れた点の一つは、取引できる通貨の種類が多いことです。そのため、自分の拠点となる取引所以外で様々なコインの取引を検討している人には使いやすく、また、他では手に入らないようなマイナーなコインにもチャンスがあります。 メリット2 口座開設が簡単 Binance(バイナンス)は、口座開設時にユーザーの本人確認を必要としない暗号通貨取引所です。必要なのは、メールアドレスやパスワードなどの基本情報だけで、FacebookやGoogle+などのユーザー名とパスワードの組み合わせサイトを使って作成することができます。これにより、海外市場で暗号コインを取引する際に、個人情報をあまり明かさずに完全なプライバシーを確保したいと考えるトレーダーに、他の取引所よりも簡単に匿名性を提供することができます。 3つ目のメリットは、取引手数料が0.1%と低いことです ユーザー同士が売買するので、どんな取引でもスプレッドが発生しないので、お得です。その代わりに、「Binance Coin」というトークンを使って手数料を支払えば、他の利用者との交換頻度に応じて50%以上の割引が受けられます。
Virtualmoney.jp is copyrighted
これは、誰かが私たちの同意なしに私たちのコンテンツを複製するテストです。 Virtualmoney.jpのコンテンツは著作権で保護されており、当社の同意なしに第三者が使用することはできません。
Uniswap(ユニスワップ)とは?
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の分散型取引所であるUniswap(ユニスワップ)の仕組みなどを詳しく解説していきます。
Liquid by Quoine(リキッドバイコイン)とは?
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の分散型取引所であるLiquid by Quoine (リキッドバイコイン)の特徴やメリットなどを詳しく解説していきます。
Kraken(クラーケン)とは?
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の分散型取引所であるKraken(クラーケン)の特徴やメリットなどを詳しく解説していきます。
Coinbase(コインベース)とは?
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の分散型取引所であるCoinbase(コインベース)の特徴やメリットなどを詳しく解説していきます。
Binance(バイナンス)とは?
本記事では、暗号資産(仮想通貨)の世界有数の取引所であるBinance(バイナンス)の特徴やメリットなどを詳しく解説していきます。
Bitcoin cash(ビットコインキャッシュ)とは?
ビットコインキャッシュ(単位: BCH )は 2017年8月に誕生した仮想通貨です。名前に「ビットコイン」が含まれますが、いわゆる「アルトコイン(※)」の一銘柄です。
Cardano(カルダノ)、ADA(エイダ)とは?
カルダノは、「プルーフオブステークブロックチェーン」と呼ばれるネットワークです。
THETA(シータ)とは?
2018年に公開された仮想通貨であるTHETA(シータ)は、ブロックチェーンを活用した「非中央集権的な動画サイトの構築」を目標とする仮想通貨プロジェクトです。